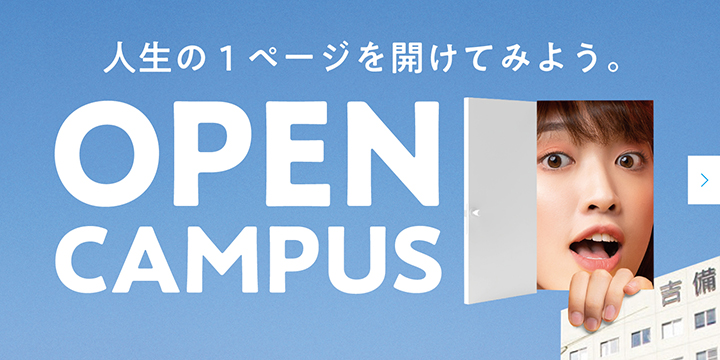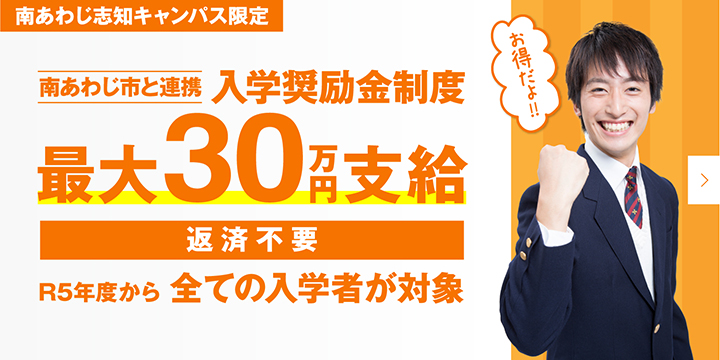公開講座
吉備国際大学公開講座 令和4年度(前期)まちなかゼミナール
本年も「まちなかゼミナール」を開講します。各講座30分程度で、どなたでも楽しめる内容となっております。尚、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前期分については、オンライン(インターネットによる動画配信で、パソコン、タブレット端末、スマートフォンによる視聴での受講)にて動画(約30分)を配信いたします。
全講義受講料無料です。
講義科目の受講方法(第1回目~第6回目前期講座)
☞申込期限:令和4年6月1日(水)※申込期限後もお問合せください。
☞申込方法:お申込みの際に、氏名、住所、電話番号、受講希望講座をお知らせください。
☎吉備国際大学庶務課(☎0866-22-7404)平日午前9時から午後5時
✉kiu-syomu@office.jei.ac.jp
※お申し込み頂いた方に動画を視聴するためのパスワードをお知らせいたします。
☞個人情報の取り扱いについて
取得した個人情報については、個人情報保護の観点から厳重に管理いたします。また、以下の目的以外では使用いたしません。①本講座への登録・受講に関する連絡②今後のまちなかゼミナールの案内・統計情報の作成
※動画の視聴には、パスワードが必要となりますので、必ずお申込みください。
内容と講師
第1回:2022年6月5日(日)配信
ココロとカラダの元気をつくろう!リハビリテーション
保健医療福祉学部 山本 倫子先生
「日々の生活を楽しく元気に過ごしたい」そんな風に考えた時、あなたは、何から始めますか?運動?頭の体操?食事?口腔ケア?趣味?どれも間違いではありません。現在すでにご自身の健康に取り組んでいらっしゃる方も多いと思います。健康づくりのレシピのコツと、健康づくりの効果を最大限に引き出すコツについてリハビリテーションの視点からお話いたします。
第2回:2022年6月12日(日)配信
食卓にスパイスを~インド料理の基本スパイスとその効用~
外国語学部 大下 朋子先生
食事はわれわれの身体とこころを健康に保つために最も大切な営みです。「アーユルヴェーダ」は「生命の科学」と訳され、生命を守り育てる知恵としてインドで発達した伝統医学です。その中でも、スパイスは身体の調子を整え、健康に導くものとされ、「病気を予防する」という観点から重要視されています。食卓にスパイスの香りと味わいを添え、健康の維持増進を目指しましょう。インド料理の基本スパイスとその効用、手軽な調理法などをご紹介します。
第3回:2022年6月19日(日)配信
アニメでつなぐ日本と世界
アニメーション文化学部 井上 博明先生
コロナ渦で激減しているインバウンドですが多くの海外の方が日本にいらしゃる理由の上位に日本のアニメを観て日本に行きたいと思ったとおっしゃっています。1963年の鉄腕アトムから始まって最近の鬼滅の刃まで多くのアニメが海外で人気を博していて、その理由と日本での効果を紹介致します。
第4回:2022年6月26日(日)配信
地域とスポーツ・健康について
社会科学部 天岡 寛先生、太田 真司先生、羽野 真哉先生
スポーツ活動は、健康の維持・増進に寄与しています。スポーツは「する」だけでなく、「見る」ことや「支える」こともその活動になります。本学科では、「支える」活動として学生が主体となった「健康教室」や「地域部活動」があります。また、「総合型地域スポーツクラブ」に所属して地域のために活動しています。地域の方々の笑顔と活気の溢れる街づくりのために学生たちが取り組む「支える」スポーツの様子をお話しします。
第5回:2022年7月3日(日)配信
聴き上手になろう
心理学部 土居 正人先生
例えば、日常で友達から悩みや相談をされた時、私から「こうしてみたら?」とアドバイスを伝えたら、友達から「そうじゃなくて!」と言われたことはありませんか?
その時、私の気持ちとしては「じゃあどうすればよいのよ!」と思うかもしれません。しかし、これは、友達の話を十分に聞きとれていないことから起こる現象です。本講義では相手とのコミュニケーションをとる際の「話の聞き方(傾聴)」についてお話します。
第6回:2022年7月10日(日)配信
なぜ、植物工場産?
農学部 許 冲先生
少子高齢化問題の深刻化による労働力不足は日本の農業にも大きな影響を与えています。このような問題を解決して、将来的に農業人口を増やすためには、省力かつ高品質生産を実現できる新しい形の農業を始めることが必要になります。そこで、人工的に環境を制御することで周年栽培を可能にし、安定した収量を確保できる「植物工場」の概念を導入します。植物工場とは一体どのようなものなのか、そして日本の農業の将来を背負う存在になれるのかどうかなど、植物工場について紹介したいと思います。