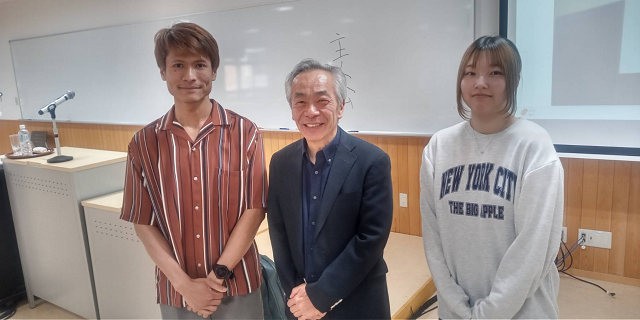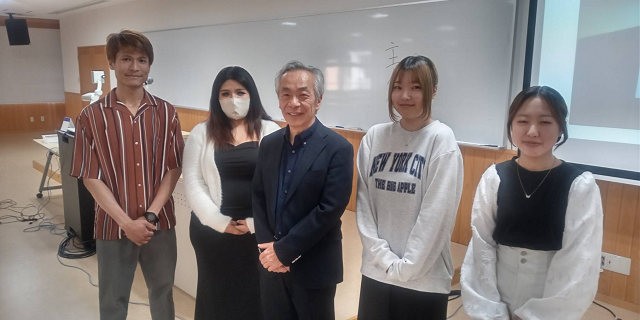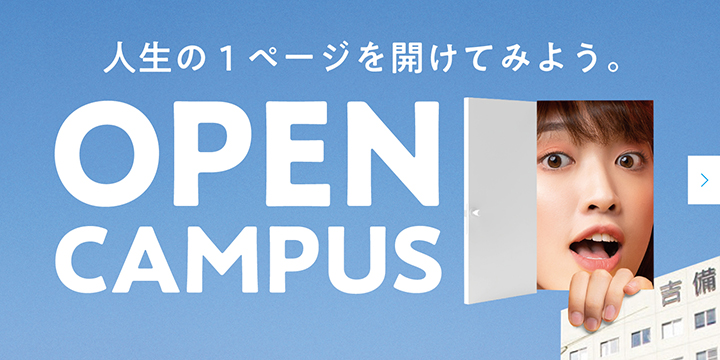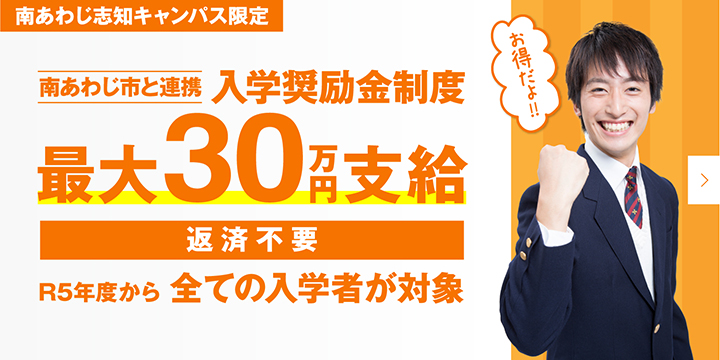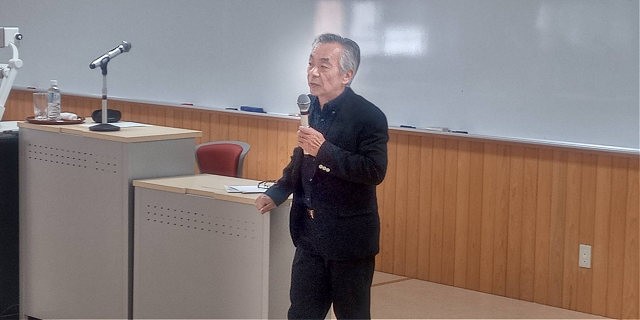キビコクNEWS
【外国学科】 生き方 栗栖基先生 自分の運命は変えられる
- 外国学科
5月14日(水)の「生き方」の授業は、京都にある京料理「嵐山 熊彦」の三代目店主・料理人、栗栖基先生にご講義いただきました。先生は、店長(社長)の職責を担いつつ、カウンターで料理・接客をされています。
冒頭、栗栖先生から、生きていく上で一番大切なことは、幸せになることと、お話しされました。そして、人類の誕生から現代までの大きな歴史の流れの中で、人類と動物との違いの視点で、どのような進化を経てきたのかを考えました。共感力があり、共食という特徴を持つ人類が、どのように進化したのか。生きる=食べる。人類は当初、狩猟採集民で、食べ物がなくなれば移動をせざるを得なかった。食べ物が原因で争いが絶えなかった。穀物が栽培できるようになり、保存ができるようになると、人類は集団で定住を始めた。人口爆発となり、食べ物が不足し争いが増えた。定住集団が大きくなり、ことば(言語)が高度化し、中央集権国家ができてきた。定住化の起爆剤であった農業の発展により、万人が便益を受ける「文明」が生まれた。共感力を高めるものが、文化であり、その発展をみた。文明を生み、文化を発展させた人類であるが、負の側面も大きくなった。争いである。人類はどこで間違えたのであろうか?いずれにせよ、歴史を振り返ると、人類は、自然環境の中で、生かされている。
消費と浪費の違いを考えてみたことはあるだろうか?消費は必要な物を買いそろえるなど、ある意味、主体性がない。一方、浪費は真なる楽しみである。本当にやりたいこと、欲しいものを獲得している。ぜいたくができる。その意味で、浪費には主体性がある。では、幸せになるとはどういうことであろうか。幸せになる、ならないは、自分次第である。各人それぞれ異なる。本当の幸せは、満足を与える。自分の幸せは自分で見つけるものだ。あることを好きになり、幸せな気持ちになると、楽しむことになる。たくさん勉強(けいこ、訓練など)すると、いろいろ経験し、知識を得て、より一層幸せになる。それが繰り返され、アマチュアからプロになる。プロになってはじめて、主体性の存在である「主人公」となる。私たちはついつい結果を見て判断するが、大切なのはプロセスである。このプロセスにおいて、たくさんの引き出し(経験、知識)を獲得する。結果だけをみてしまうと、運命ではないかとの懸念が生まれるが、引き出しがあれば、自分の運命は変えられる。楽しい幸せを目指して欲しい。
最後に、栗栖先生は、佐々木元果和尚との出会いがあり、師と仰がれていた。一期一会を大切にして欲しいと、講義を締めくくられた。
質疑応答では、学生から、「消費と浪費の違いを教えていただきました。その上で、先生にとって、ぜいたくとわがままの違いは何でしょうか。」と質問があり、栗栖先生からは、『ぜいたくはそれ自体問題はないが、ぜいたくをすることにより、他の人にマイナスの影響を及ぼすことになるとすれば、それは「わがまま」と言えるのではないでしょうか』、との回答がありました。
講義コメントから、いくつかを紹介します。
・楽しいと感じることが幸せだと教えていただいた。自分にとって幸せとは何だろうか、考えてみたい。
・共感力が人間を人間たらしめたもの。誰かの心に寄り添える人でありたいと願っています。(留学生)
・何事も楽しむためには勉強をして知識を積めることが大切だと分かりました。いろんな体験をして本当の楽しみを見つけていきたいと思いました。
・勉強ができる今を大切にしたい。
・自分のために自分の人生をどう生きるかについて、もっと関心を持たないといけない。
・楽しみながら、その道のプロになれるよう歩んでいきたい。
・自分の運命は自分でしか変えられない。(留学生)