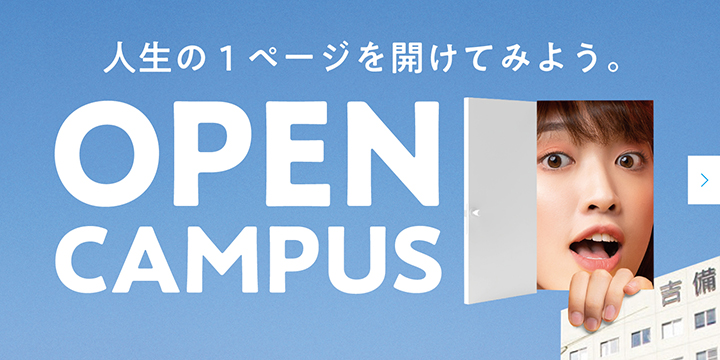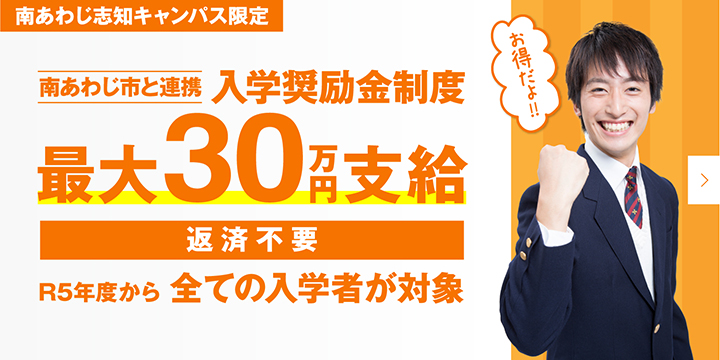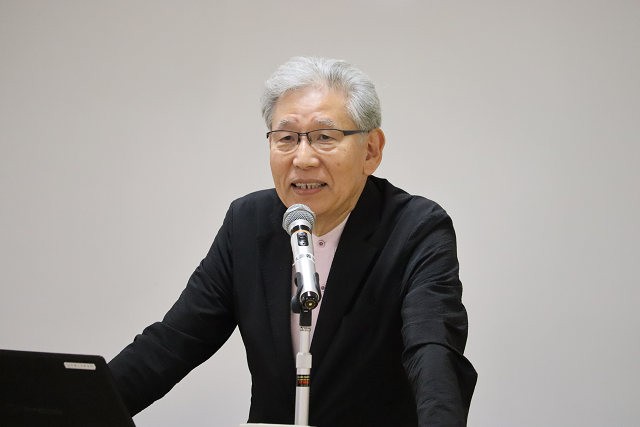キビコクNEWS
【外国学科】漆芸作家(人間国宝)室瀬和美先生の「生き方」講義 「漆に魅せられて」
- 外国学科
外国語学部外国学科の授業科目「生き方」にて、人間国宝 室瀬和美先生による授業が、7月16日、岡山キャンパス(岡山市北区)にて行われました。本年度授業としては第13回目になります。
室瀬先生はまず、漆(うるし)は英語でlacquerと訳されるが、漆の生育地域や化学成分の点で異なるもので、適切な訳でない旨説明された。敢えて漆を英語にするのであれば、urushiまたはurushi-lacquerと言うべき。この表現は、徐々にではあるが欧米の専門家の間で使われるようになった。漆は固まると強くなり、長持ちする特徴がある。漆を使った工芸品は数千年の歴史があり、最も古いものは日本で発掘されている。東アジアの長い歴史と共に存在してきたもの。あまり知られていないが、16世紀には、漆工芸品である漆器がヨーロッパに多く輸出されている。有名なものとしては、マリー・アントワネット・コレクションがある。
古代の漆芸品が東大寺正倉院に所蔵されている。伝世品である。そして、1300年前の漆芸技術が残っている。有形の工芸品と無形の技術が同時に残っているのは、日本だけである。日本の強みである。古い物を残すだけでは文化は残らない。作る技術が必要。伊勢神宮の遷宮のように、定期的につくり直すから技術が残る。能登半島の輪島市には、漆芸家の多いところ。能登半島地震で被災された。困難の中、漆芸を続けられている。この事例が示すように、これからの工芸文化は、「つなげる努力」が重要だ。
自然との関わりは,人間の感情を豊かにする。この関わりは漆から学んだ。自然の素材をもとに、お椀などの漆器を作り、使用する。使えなくなったら、自然に戻す。土に戻った漆器は、漆の木を育て、新たな素材を提供する。
終わりに、室瀬先生は、ご自身の生き方を振り返り、学生へのメッセージをいただきました。現在、漆芸家として活動しているが、この道に進むべきかどうかは、高校2年生の時に決断した。漆芸家の父親に相談すると、「やめろ」と言われた。高校の先生に相談しても同じであった。誰に相談しても賛成する人がいなかった。その中で、漆に親しんでいた先生は、漆とは何だろうか、分からないことが多いが、おもしろそうだ、漆は不思議だ、と。やってみるとおもしろい。その際、やることを決める重要さと怖さを同時に経験した。迷いは最初のみで、やり始めると止まらない。人の倍努力すればものになると信じて決断した。特定の分野で成功するためには、「好きなことをやる」こと、「人のやらないことをやる」勇気が必要。自分の好きなことを続けてください、集中して取り組んでください。必ず、報われる。
学生からいくつか質問がありました。最初の質問は、室瀬先生は海外でご活躍されていますが、海外で回答に困った質問はどのようなものがありましたか。これに対して、先生から、欧米では多くの質問やコメントがあり、うれしい悲鳴となるが、困るのは、プライベートな質問である、と。さらに、漆芸作品のデザインはどこからインスピレーションを得られていますか。先生は、自分のデザインは自然のものを題材にしている。そのまま使うのではなく、空気感を大切にしています、と。次の学生は、作品制作にどれぐらいの時間がかかるのか,と質問がありました。作品の大きさにはあまり影響されず、2年半ぐらいはかかるとのこと。また、ベトナム人留学生から、若い自分たちに、生き方のコツを教えてもらいたい。先生からは、自分の失敗をムダにせず積み重ねて欲しい。失敗しなくなる。ベトナムでも漆がとれる。少なくなったようですが、漆芸家もいらっしゃる。ベトナムの文化として大事にしてください。日本との交流も期待したいとの付言がありました。
外国語学部外国学科では、「先達に学ぶ、人生のより良い『生き方』」をテーマとし、これまで日本を創ってきた人々、豊かで平和な社会を築いてきた人々の<生>の声を聞き、学生一人ひとりが、この国や社会のためにできることは何か、また自らが幸福な人生を送るために何をすればよいのか…等、それぞれが自分のあるべき将来について考える。そうすることで、今の自分を見つめ直すことができるようになる。また、自分の<志>を確認できるようになることを目標に、外国学科学生の必修科目として「生き方」を開設しております。