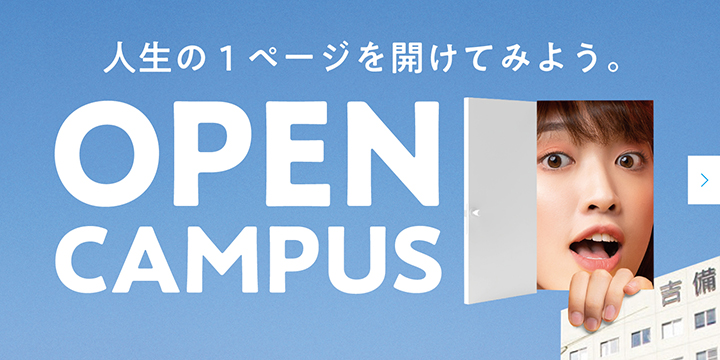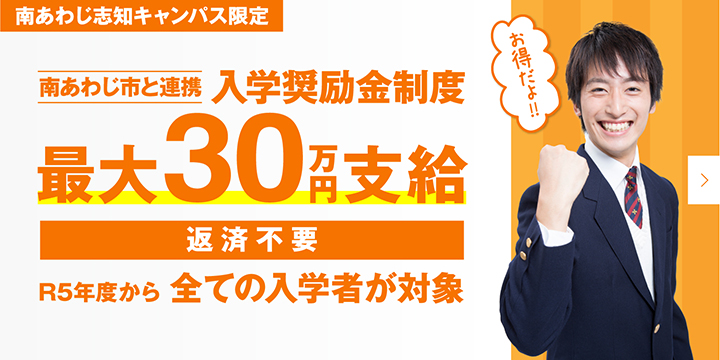キビコクNEWS
【外国学科】ワイン醸造家 大岡弘武先生の「生き方」講義「フランス・ワインに魅せられて」
- 外国学科
外国語学部外国学科の授業科目「生き方」にて、ワイン醸造家 大岡弘武先生による授業が、7月23日、岡山キャンパス(岡山市北区)にて行われました。本年度授業としては第14回目になります。
大岡先生はまず、講義のポイントを示していただきました。①多様な価値観を認める、②情熱が大事、③本質を考える、④いま与えられた課題に取り組むの4点です。その上で、なぜ先生がワインに魅せられ、ワイン醸造家として活動されているのかに関し、これまでの経験を振り返っていただきました。きっかけは、大学1年生の時、ワーク・キャンプのプログラムで、フランス・ピレネー山脈の村にいき、登山者やハイカーのための観光地図をつくる活動に従事し、帰国の際、酒屋さんでおみあげとしてワインを買い求めた。帰国後、父親と一緒に味わったこのワインがあまりにも美味しく、ワインに出会い、ワインにはまったそうです。大学在学中は、専門の勉強をしつつ、ブドウやワイン醸造を夢中に学ばれたそうです。
大学卒業後、フランスのワインの一大産地のある中心都市ボルドーにある、ボルドー大学醸造学部に進学されました。そこでワイン醸造の専門知識と技術を学ばれました。同大学卒業後、ワイン醸造家になるべく、師匠を探されました。ティエリー・アルマン氏に師事することを決め、アルマン氏にお願いに行きましたが、見事に断られました。この世界は甘くない。自分には今、なにもないけど、情熱だけはある。断られてもあきらめないと自分に言い聞かせ、アルマン氏のブドウ畑の近くに畑を借り、機会をうかがった。半年が過ぎたころ、同氏の目に留まり、教えてもらえることになったそうです。やる気、つまり、断られてもあきらめないことが大切。
ブドウ畑を購入するためには大きな資金が必要でしたが、比較的安く購入できる未開拓の斜面3haを取得しブドウ畑にすることを勧められた。木が多く茂っていたところを、伐採、伐根しブドウ畑にしたそうです。ブドウの苗木を植えて間もないころ、大雨に襲われ、土が流出しましたが、流された土を畑に戻し、ブドウ栽培を再開した。情熱があったから、難題が降りかかっても克服できた。あきらめなかった。家を購入したが、自分たちでリフォームし、住み心地の良い家にした。フランスでは自分で家をつくったり、改修したりするのは当たり前で、自分もそれにならったとのこと。ブドウの有機栽培を行い、ナチュラル・ワインをつくることを学ばれたそうです。化学肥料、除草剤、殺虫剤、化学薬品、GMO種を使わない栽培手法は難しい課題の連続だったようです。土とは何か?と、常に考えていたそうです。
大岡先生は、20年近くフランスでワインつくりに励まれましたが、いくつかのことが重なり、日本に帰国することになった。老後は日本が良いだろう、と。岡山でブドウ栽培の適地を探し、ワインつくりを始められました。フランスのブドウはフランスの気候だからうまく育つ。日本では日本の気候風土に合ったブドウの品種があるはずだとの信念で、新品種を育種家の方と共同で開発されました。いかに病気に強く、栽培しやすい品種を特定するかが課題だった。ワイナリーの諸施設・機材は、可能な限り、ネットオークションで購入し初期投資額を抑える工夫をした。このやり方でないと、資金的な困難性が高く、後に続く人たちが生まれない。多くのことにチャレンジされてきました。小学生によるぶどう踏み体験を毎年開催されたり、四国の柑橘類を原料に柑橘酒を醸造するなど。ワインつくりをしてみたい人のために、2021年に「おかやま葡萄酒園」を開設し、運営されている。会員が主体に運営する団体で、みなさん楽しんでやっている。土を触るといろいろな気付きがある。岡山をワインの産地にするという夢がある。
学生との質疑応答のセッションがありました。ひとりの学生から、「年明けに、フランスに留学しますが、先生おすすめのワインはありますか?」との質問があり、大岡先生からは、「ブルターニュに留学されるのであれば、近くのロワールの白ワインを試してみてはどうでしょうか。」とアドバイスがありました。そして、「先生は多くのことにチャレンジされてきましたが、リスクのある中で、困難との向き合い方はどうされていましたか?」との質問がありました。大岡先生からは、経験を振り返り次のとおり回答された。自分は好きでやっていた。「やりたい」の気持ちがリスクよりも大きければよいだけ。最悪のことを考え検討はした。しかし、困ったことが起きると、回りが応援してくれるもの。何とかなるものです。ベトナム人留学生からは、ワイナリーを起業されたが、何が大変だったでしょうか?と質問がありました。先生からは、難しかったことは、技術ではなく、資金ではなく、地域の人々の信頼をいかに得られるかという点だった。地域との繋がり、コミュニティーとの付き合い方が、正直言って難しかった、と。
最後に、大岡先生から、「自分はこれまでがむしゃらにやってきた。決められた道だったのかもしれないと思うほどだ。やっていれば何とかなるものだ。苦手のことは少しずつ乗り越えてきた。学生のみなさんは、将来のことは不安かもしれないが、がむしゃらにやっていれば何とかなる。大いにチャレンジしてもらいたい。」と、学生がエールをいただきました。
外国語学部外国学科では、「先達に学ぶ、人生のより良い『生き方』」をテーマとし、これまで日本を創ってきた人々、豊かで平和な社会を築いてきた人々の<生>の声を聞き、学生一人ひとりが、この国や社会のためにできることは何か、また自らが幸福な人生を送るために何をすればよいのか…等、それぞれが自分のあるべき将来について考える。そうすることで、今の自分を見つめ直すことができるようになる。また、自分の<志>を確認できるようになることを目標に、外国学科学生の必修科目として「生き方」を開設しております。